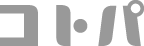Page 2 of 22
エイミー・C・エドモンドソン
ジョン・マクスウェル
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソン
エイミー・C・エドモンドソン
ジョジョ
ジャック ウェルチ